4 農林漁業や食生活、食料の生産、流通、消費に関する統計調査等の実施・公表
農林水産省は、食育を推進する上で必要となる農林漁業の姿や食料の生産、流通、消費に関する基礎的な統計データを広く国民に提供し、食育に対する国民の理解増進を図っています。主なものとしては、米や野菜など主要な農畜産物の生産や流通に関する調査、魚介などの水産物の生産や流通に関する調査を実施し、公表しています。
また、食育に関する国民の意識を把握するために、「食育に関する意識調査(*1)」を実施し、調査結果を公表しています。
環境省では、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)(*2)」として、化学物質のばく露等の環境要因が子供の健康に与える影響を明らかにするため、平成22(2010)年度から10万組の親子を対象に、質問票によるフォローアップ等を行っています。その一環として食生活を含めた生活環境についても調査しており、その研究結果を公表しています。
1 食育に関する意識調査(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki.html
2 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)(環境省):https://www.env.go.jp/chemi/ceh/index.html(外部リンク)
コラム:「令和元年国民健康・栄養調査」結果の概要
「国民健康・栄養調査」は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため実施する調査です。
平成25(2013)年度から開始している「健康日本21(第二次)」では、国民の健康の増進の推進に関する基本的方向の一つとして、「栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善」を盛り込み、ライフステージや性差、社会経済状況等の違いに着目し、対象集団ごとの特性やニーズ、健康課題等の把握を行っています。
その「健康日本21(第二次)」の中間評価において、生活習慣の改善には、これまでの施策で行動変容がおきていないと思われる無関心層へのアプローチが課題であることが示されました。個人の置かれている状況を踏まえつつ、生活習慣の改善を促す施策を検討するため、令和元(2019)年の調査では、社会環境の整備に関する実態把握を重点項目として「食習慣」についての関心度やその変容の阻害要因等を把握することとしました。また、全国各地で大規模な災害が発生していることを踏まえ、家庭における非常用食料の用意の状況についても把握しました(*1)。
1 令和元年「国民健康・栄養調査」の結果(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14156.html(外部リンク)
<食習慣改善の意思について>
食習慣改善の意思について、「関心はあるが改善するつもりはない」者の割合が最も高く、男性で24.6%、女性で25.0%でした(図表1)。
健康な食習慣の妨げとなる点を食習慣改善の意思別にみると、「改善するつもりである」者及び「近いうちに改善するつもりである」者は、「仕事(家事・育児等)が忙しくて時間がないこと」と回答した割合が最も高い結果でした(図表2)。
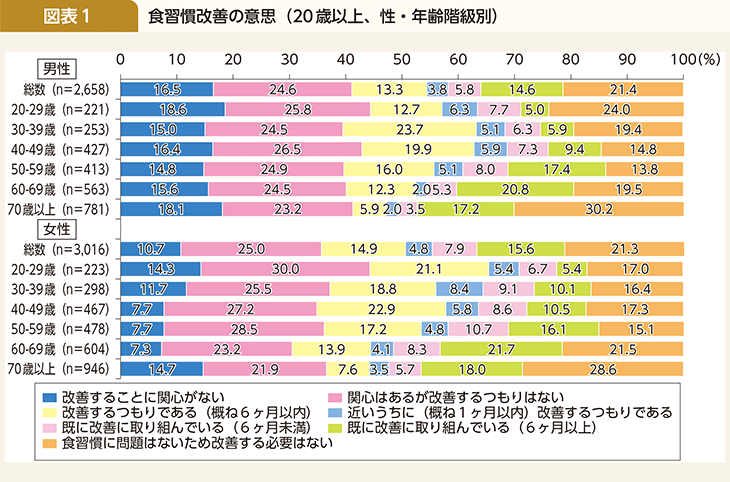
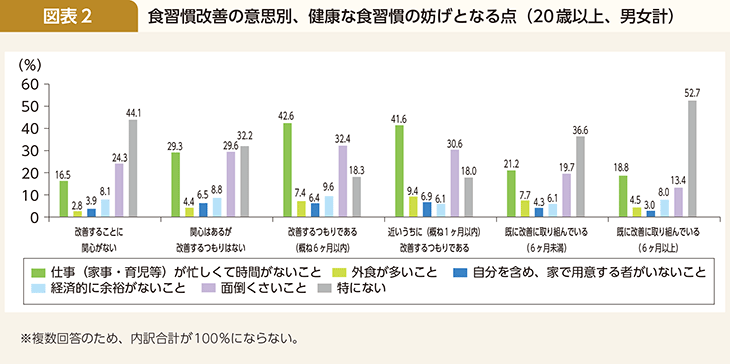
<非常用食料の用意の状況について>
災害時に備えて非常用食料を用意している世帯の割合は53.8%でした。地域ブロック別にみると、最も高いのは関東Iブロックで72.3%、最も低いのは南九州ブロック33.1%でした(図表3)。
非常用食料を備蓄している世帯のうち、3日以上の非常用食料を用意している世帯は69.9%でした。
「国民健康・栄養調査」では、引き続き実態の把握を行い、様々な取組の推進に役立つデータを発信していきます。
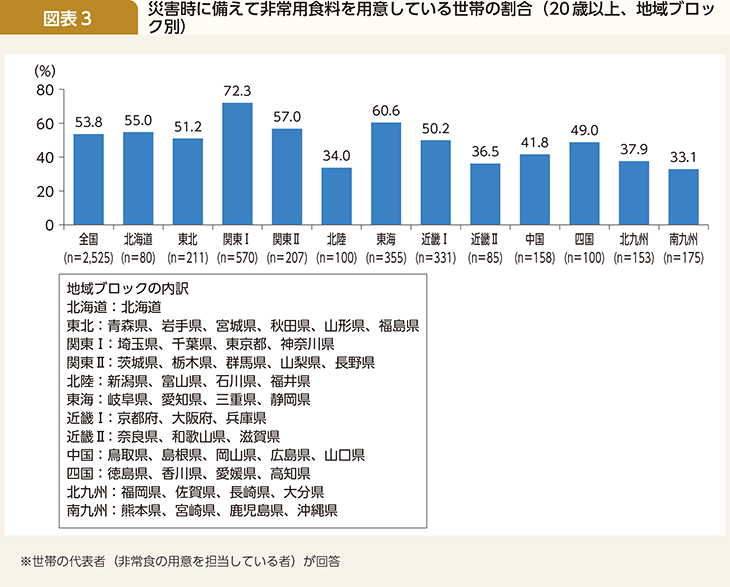
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974




